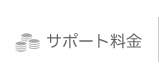仕事が原因でメンタル不調になった方

厚生労働省が公表した令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、「現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある」と回答した労働者の割合は82.7%となっています。現代においては、労働者の多くが、仕事に関することで強いストレスを感じながら仕事を行っている状況にあるといえます。
仕事上のストレスにより、精神障害を発病し、あるいは悪化させて、解雇や休職を強いられれば、その方の収入は途絶えてしまうことになります。また、症状が改善し、いざ復帰しようとしても、会社から復職を認めてもらえなかったり、そのまま退職を強要されたりするケースも往々にしてあります。
このように、仕事を原因としたメンタルヘルス不調の問題は、労働者の生活に大きく影響を与えるにもかかわらず、労働者の皆様が法的サポートを十分に得られていないケースは多いです。
参考:厚生労働省|令和5年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概要
労災による補償
長時間労働やパワーハラスメントといった仕事上の強いストレスにより、うつ病などの精神障害を発病してしまった場合、それが労災として認められれば、治療費や休業損害などの補償を受けることができます。
さらに、労災で治療のために会社を休んでいる期間と、復職後30日間は、会社は労働者を解雇することが原則として禁止されています。
このように、労災の認定を受けることで、治療に専念するための様々な補償を確実に受けることができるのです。
したがって、仕事上の強いストレスが原因と考えられる場合には、労災申請を検討すべきです。
ただし、精神障害の労災認定は、事故による怪我の場合などと異なり、労働基準監督署による調査に時間がかかるため、申請してから認定されるまで長い時間がかかる(半年~1年程度)傾向にあります。
そこで、労災が認定されるまでの当面の生活費を確保するため、健康保険の傷病手当金の申請を同時に行うことをお勧めいたします。
傷病手当金は、業務外の傷病により労務不能となり、給料が支給されない場合に、健康保険から給料の約3分の2が支給される制度です。傷病手当金は、勤務先の証明と主治医の意見を記載してもらった申請書を提出し、通常1~2か月程度で支給されます。
当面はこの傷病手当金を受給しながら生活し、労災が無事認められた場合には、労災保険給付から傷病手当金を返還すればよいことになります。
どのような場合に労災と認められるのか
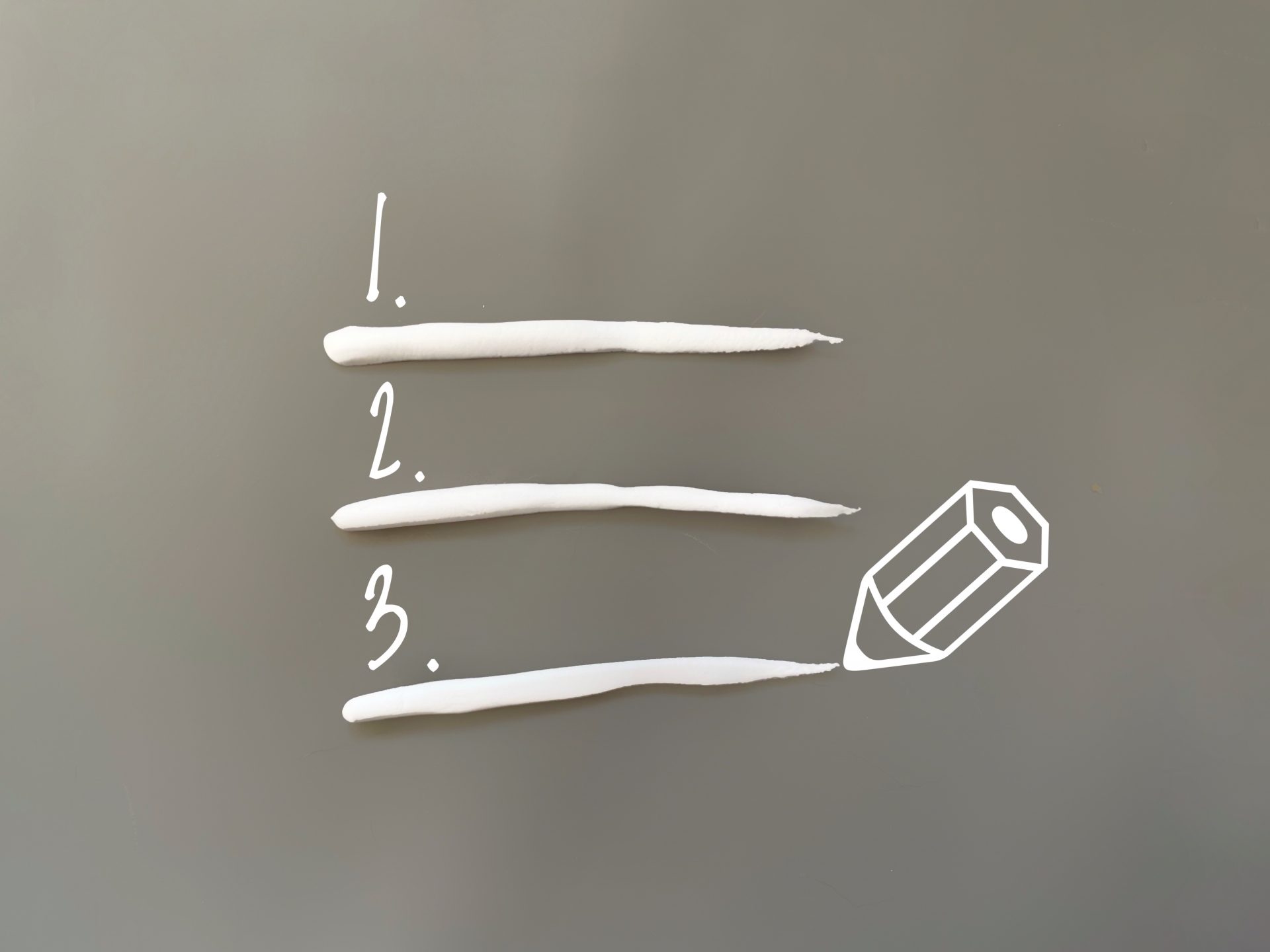
うつ病などの精神障害は、外部からのストレスとそのストレスへの個人の対応力の強さとの関係で発病に至ると考えられています。
そして、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断される場合には、発病した精神障害が労災として認められます。
精神障害が労災として認定されるための要件は、以下の3点です。
(1)対象となる精神障害を発病していること
気分障害(うつ病、うつ病エピソード、躁うつ病など)、統合失調症、パニック障害、急性ストレス反応、適応障害、統合失調症などの精神障害を発病したことが必要です。
そのため、まずは病院で受診し、労災認定の対象となる病気を発症したことを証明する診断書を医師に書いてもらいましょう。
ただし、医師が診断書に病名として記載すれば必ずその通り認められるというものではなく、カルテ等の資料や、本人・関係者からの意見聴取などを通じて事実確認が行われ、総合的に発病の有無や発病時期が認定されます。
(2)精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷(ストレス)が認められること
発病の原因となる心理的負荷の要因には、重大な事故・ミス、長時間労働、ハラスメントなど、様々な事情が挙げられます。これらの業務による心理的負荷の強度が、総合評価で「強」と判断されることが必要です。
厚生労働省は、「業務による心理的負荷評価表」により、負荷の類型ごとに、どのような事情があれば、どの程度の心理的負荷の強度が認められる、という目安を定めています。
まず、業務の中で、生死にかかわる病気やケガをした・負わせた、性的暴行やわいせつ行為を受けた、極度の長時間労働(発病前1か月に160時間、3週間に120時間を超えるような時間外労働)を行った、などの特別な出来事がある場合には、それだけで心理的負荷の総合評価は「強」と判断されます。
また、それ以外の出来事については、具体的出来事を上記の評価表に当てはめて評価を行います。業務により重度の病気・ケガをした、業務上重大な事故を起こした、重大な仕事上のミスをした、違法行為を強要された、達成困難なノルマを課された、長時間労働や連続勤務を行った、退職を強要された、パワハラ・セクハラ・カスハラや嫌がらせ行為を受けた、などの出来事について、具体的な事情や、事情が関連する程度を考慮した上で、「強い」心理的負荷といえるのかが判断されます。
長時間労働についていえば、連続した2か月に月120時間以上、連続した3か月に月100時間以上の時間外労働、1か月以上の連続勤務、2週間以上の連続勤務かつ深夜残業が認められる場合、「強」と評価されます。
(3)業務以外に発病の要因(業務以外の心理的負荷や個体側要因)がないこと
業務以外の心理的負荷が発病の要因でないかどうかの判断に当たっては、「業務以外の⼼理的負荷評価表」が用いられています。
配偶者と離婚した、重い病気になった、流産した、身内に不幸があった、多額の借金を負った、犯罪に巻き込まれたなどの事情があり、業務以外に強い心理的負荷があったと認められると、それが発病の要因であったと判断される可能性があります。
また、精神障害の既往歴がある、アルコール依存症であったなど、もともと精神障害を発病しやすい個体側要因がある場合には、それを原因とする発病でないかについて慎重な判断がなされます。
ただし、精神障害の既往歴などがあったとしても、業務による強い心理的負荷があり、それが主たる原因となって精神障害が発病・悪化した場合には、労災と認定される可能性がありますので、あきらめる必要はありません。
弁護士によるサポート

うつ病などの精神障害の労災認定においては、①精神障害を発病したといえるか(特に自殺の事案などでは、病院への通院歴がないというケースもあります)、②発病時期の特定(発病前6ヶ月の出来事が原則として対象となります)、③ストレス要因の心理的負荷の強さとその裏付け(長時間労働・ハラスメントなどの立証資料の収集)、④精神障害の既往歴や業務外原因の有無など、様々な点が問題になります。
したがって、労災の申請・認定の場面においては、労働問題に精通した弁護士に相談し、そのサポートを得ることが望ましいでしょう。
また、そのほかの場面でも、弁護士は、労働問題の専門家として、メンタルヘルスの不調を訴えられている皆様に対して様々なサポートをすることが可能です。
例えば、うつ病になり休職を開始した後、そのことを理由として解雇された、休職からの復帰が認められず休職期間満了で退職扱いとなった、復職後に賃金引き下げ・配置転換などの不利益な扱いを受けた、といったケースでは、使用者(会社)側の処分の効力を争うことが考えられます。
また、復職に向けて、職場の労働環境や人間関係などについて、使用者側と調整・交渉することが必要なケースがあります。
さらに、精神障害の発病について、使用者側に、安全配慮義務違反(労働者の健康確保に配慮し労働環境などを整える義務を怠ったこと)や、従業員の不法行為についての使用者責任が認められる場合には、会社に対して損害賠償を請求することも考えられます。
上記のような場面では、弁護士から適切な法的アドバイスやサポートを受けることで、問題を解決できる可能性があります。
メンタルヘルスの不調で、どうすれば良いか分からなくなってしまったら、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
なお、精神障害の影響などにより、ご本人様自身では、弁護士に事実経過を話したり、ご自身のお考えを整理して表明することが難しい場合もあると思います。そのような場合には、ご家族やご友人に同席していただき、代わりにご説明等をいただいても問題ございませんので、ご安心ください。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
24時間受付