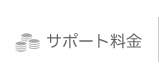会社へ損害賠償請求をお考えの方

使用者(会社)に対して損害賠償請求ができる場合
労災と認められた場合であっても、必ずしも使用者(会社)に対して損害賠償請求ができるわけではありません。
使用者に対する損害賠償請求が認められるためには、使用者に「安全配慮義務違反」や「使用者責任」が認められることが必要です。
安全配慮義務違反
使用者は、労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすべき義務(安全配慮義務)を負っています(労働契約法5条)。
労働災害について、使用者に「安全配慮義務違反」があれば、被災した労働者またはその遺族は、雇用契約上の債務不履行責任(民法415条)や不法行為責任(民法709条)に基づき、使用者に対して損害賠償を請求することができます。
使用者が負っている具体的な安全配慮義務の内容は、個々の事案によって異なります。使用者の責任を問うためには、被災した状況(事故の態様)や業種、作業内容、作業環境、被災者の地位・経験、当時の技術水準など、様々な要素を考慮して、使用者がどのような安全配慮義務を負い、どのように違反したのかについて、具体的に特定し、主張立証していかなければなりません。
そのためには、労働局に対して「保有個人情報開示請求」を行い、労災に関する資料を取り寄せるなど、適切な証拠を集めることが重要となります。
なお、安全配慮義務には、業務遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を害することがないよう注意し、また、健康状態が悪化している・悪化しようとしている場合には勤務軽減などの措置により健康が増悪することのないよう配慮すべき義務(健康配慮義務)が含まれるとされています。
したがって、使用者が、長時間労働を課す、過大な業務量やノルマを課す、適正な人員配置を怠る、劣悪な労働環境で勤務させる、ハラスメントを放置する、健康管理を怠るなどしたことにより、労働者が心身の健康を害したようなケースでは、使用者の安全配慮義務違反を問うことが十分に考えられます。
使用者の安全配慮義務違反を問えるかどうか、ご不明な方は、ぜひ一度、専門家である弁護士にご相談ください。
使用者責任
業務に関連して、他の従業員の故意・過失による行為によって怪我をした・病気になった場合には、その従業員に対して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求ができるとともに、使用者に対しても、使用者責任(民法715条)に基づき、損害賠償を請求することができます。
例えば、業務中に他の従業員から暴行を受けて怪我をした、他の従業員による機械の操作ミスによって怪我をした、他の従業員のハラスメント行為によって病気になった、などのケースでは、使用者の使用者責任を問うことが考えられます。
使用者(会社)に対して何が請求できるか

労災による怪我や病気について、労災保険から給付を受けている場合、その限度で使用者の損害賠償責任は免責されます。
もっとも、労災保険では、怪我や病気によって生じる損害のすべてを補填することはできません。このように、労災保険では補填しきれない部分の損害については、使用者が損害賠償責任を負うことになります。
具体的には、以下のような損害の賠償を請求することが考えられます。
精神的損害(慰謝料)
労災保険では、怪我や病気の治療を強いられたことや後遺障害が残ったこと、あるいは亡くなったことに対する精神的損害(慰謝料)は、補償の対象外とされていますので、使用者に対して賠償を請求することになります。
休業損害、逸失利益
労災保険では、休業補償については平均賃金の60%、後遺障害が残った場合の障害補償や亡くなった方の遺族に支給される遺族補償についても将来の逸失利益の一部しか給付の対象ではありません。実際の損害額と労災保険給付との差額については、使用者に対して賠償を請求することになります。
その他
治療費は労災保険から給付されますが、入院雑費、付添看護費、通院交通費・宿泊費、装具・器具購入費、家屋・自動車改造費などの損害は、労災保険から給付されませんので、使用者に対して賠償を請求することになります。
過失相殺
被災した労働者の側に一定の落ち度(過失)が認められる場合には、その分が損害額から減額されることになります。労働者にも損害の発生・拡大の原因があるのであれば、その損害の全額を使用者に負担させることは不公平と考えられるからです。このことを「過失相殺」といいます。
使用者に対する損害賠償請求の場面では、使用者からこの過失相殺を主張されることが多くあります。ケースによっては、賠償金額が大きく減額されてしまいます。
したがって、労働者の過失の程度が軽いにもかかわらず、使用者から大きな減額を主張されたときには、過失の割合についてきちんと争っていくことが重要になります。
損害賠償請求の流れ
使用者に対する損害賠償請求を検討している場合、まずは労災に関する資料をできるだけ収集・確保することが必要です。労働局に対して「保有個人情報開示請求」を行い、労災について労働基準監督署が調査した内容・資料を取り寄せるとともに、事故や勤務の状況に関する資料、領収書など損害に関する資料を用意していただきます。
こうした資料を基に、使用者が責任を負う根拠・内容を検討し、使用者に請求する損害額の算定を行った上で、使用者に対して損害賠償を請求する通知書を送付します。
その後、使用者と交渉を行い、話し合いで解決ができなければ、訴訟手続を通じて解決を図ることになります。
このように、適切な資料の収集、主張の組み立て、使用者との交渉・訴訟を、労働者やそのご遺族の方が個人で進めていくことは、決して容易なことではないと思います。
使用者に対する損害賠償請求をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
24時間受付