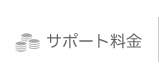労災に遭ったら、どうすればいいの?―労災保険や損害賠償について弁護士が解説
「仕事中に怪我をした」
「過酷な労働によりうつ病になった」
このようなケースでは、労働災害(労災)と認定されて、労災保険の給付を受けられる可能性があります。また、使用者(会社)に対して損害賠償を請求することも考えられます。
もっとも、実際にどのような場合に労災と認められるのか、どのような給付を受けることができるのか、手続はどうすればよいのか、使用者に対して損害賠償請求する方法など、具体的なことはよく分からないという方が多いと思います。
そこで、ここでは、労災・労災保険制度の内容や、使用者に対する損害賠償請求との関係などについて、詳しくご説明いたします。
ただし、実際にご自身で対処するとなると、不明な点や対応できない点などが出てくると思います。なるべくお早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
労災について弁護士がサポートできること
○労働災害(労災)とは?
そもそも、単なる事故や病気と労働災害との違いは何でしょうか?
労働災害は、業務が原因となって労働者がケガや病気、死亡した場合のことをいいます。
これは、就業中か否かは関係ありません。典型的なのは、就業中に事故に遭って怪我をした、あるいは死亡したようなケースですが、それだけでなく、例えば、過重労働や業務上のストレスが原因となり自宅で自殺したようなケースについても、労働災害とみなされることがあります。過重労働が原因で、脳・心臓疾患により死亡したケースは過労死、精神疾患にかかって自殺したようなケースは過労自殺と呼ばれており、それぞれ労災を認定する場合の基準が定められています。
労働災害に当たる場合、使用者は、過失の有無にかかわらず、労働基準法上の補償責任を負うことになります。
ちなみに、通勤中に起きた事故で怪我または死亡した場合、使用者は、労働基準法上の補償責任は負っていません。もっとも、労災保険では、このような場合にも業務との関連性が強く、労働者を保護する必要があることから、後述するように、給付対象に通勤災害が含まれています。
○労災保険とは?
(1)労災保険の概要
労働災害によって生じた損害の補償については、労災保険(労働者災害補償保険)という制度が設けられています。
これは、使用者に代わって、「業務」「通勤」による怪我や病気に対する補償を政府が保険給付という形で行う制度です。
労災保険の目的は、業務を原因として災害にあった労働者を守ることです。労災に対する補償は、本来は雇用している使用者が負うべき責任であり、労働基準法にそのことが明記されています。しかし、産業の高度化などにより労働者が職場で災害に遭うリスクが高まるにつれて、事業主だけでは補償しきれないケースも出てくるため、社会保険制度としての労災保険が誕生しました。これは、あくまでも労働者を保護する立場からできた社会保険制度であり、労働者の最低限の生活保障という観点から設けられているものです。
労災保険は、労働者を使用する全ての事業に適用されます。つまり、一人でも労働者を使用する事業であれば、基本的に業種や業態に関係なく強制的に適用される制度です。ただし、国家公務員や地方公務員は「公務災害」として別の法律が適用されますので、労災保険の適用はありません。
また、労災保険の適用を受ける労働者は、正社員だけを指すのではなく、アルバイトやパートタイマー、日雇い労働者なども対象になります。大工の一人親方や個人タクシーの運転手など、一定の事業者については、労働者に準じて労災保険の適用を受けられる特別加入の制度があります。
労災保険の給付を受けるためには、各種申請書を労働基準監督署等に提出し、保険請求の手続を行うことが必要です。保険請求の手続で、労働災害と認定されなければ、保険給付を受けることはできません。
(2)保険給付の対象
労災保険では、「業務災害」と「通勤災害」が主な保険給付の対象となります。
業務災害
「業務災害」とは、業務中の労働者の負傷や疾病、後遺障害の発生や死亡を指しますが、業務と災害発生による死傷病の因果関係が認められてはじめて業務災害として認定されます。その因果関係の判断にあたっては、「業務遂行性」と「業務起因性」の2点が認められる必要があります。
「業務遂行性」とは、簡単に言えば業務中に発生したケガや病気なのかということで、労働者が使用者の支配下にある状態かどうかで判断します。所定時間内や残業中に社内で業務に就いている場合はもちろん、出張中や社用での外出中であっても、業務に従事している場合は業務遂行性が認められます。
「業務起因性」とは、簡単に言えば業務がケガや病気の原因になったのかということです。社内で業務中に起こった災害は、労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが主な原因となりますので、基本的には業務起因性が認められます。ただし、例えば意図的に災害を発生させた場合や、休み時間中などの私的な行為、いたずらなどが原因で発生した災害では認められません。また、出張や社用での外出中であっても、業務に従事している際に発生する災害は基本的に業務起因性が認められますが、会社の業務とは全く関係のない私用の最中に発生した場合などには認められません。
通勤災害
「通勤災害」の対象となる「通勤」とは、「就業に関し、住居と就業の場所との往復の移動を、合理的な経路および方法で行うこと」をいいます。
「移動」には、就業の場所から他の就業場所への移動や、単身赴任先と帰省先の住居間の移動も含みます。
「合理的な経路および方法」とは、通常通勤のために利用する経路で、公共交通機関や自動車、自転車、徒歩などの通常利用できる方法を指します。移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。例えば、帰宅途中で居酒屋に寄ることや、映画館などで映画鑑賞をすることは逸脱や中断として取り扱われます。ただし、日用品の購入や通院など日常生活上必要な行為で通勤経路を外れたときには、最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤となります。
○労災保険の補償範囲
次に、具体的な保険給付の内容について確認していきます。
保険給付は、大きく分けて次の(1)から(7)に分類することができます。「補償」という文字が入っている給付が業務災害における名称で、「補償」という文字が入らないかっこ書きの方が通勤災害における名称です。
(1)療養補償給付(療養給付):治療・治療費の補償
労働者が負傷や病気により治療を必要とする場合の給付です。原則として労災指定病院で治療を行い、「療養の給付請求書」を病院窓口で提出して、かかった医療費そのもので支給を受けます。
例外として、労災指定病院以外で治療を受けた場合には、一度立て替えて支払いをした後に、労基署に書類を提出して現金の支給を受けます。ただし、立て替える金額は健康保険などの適用がなく実費での負担となるので高額になります。後々の手続きも含めると労災指定病院で治療を行う方が手続的にも金銭的にも楽になるケースが多いです。
(2)休業補償給付(休業給付):休業中の賃金補償
怪我や病気の治療のために休業したときに、休業4日目から賃金の補償として給付を受けることができます。3日目までの期間は支給されませんので、使用者が負担することになります。支給される金額は、1日につき給付基礎日額(事故発生日の直前3か月間の賃金総額をその期間の日数で割った賃金)の60%です。
また、これに加えて、1日あたり給付基礎日額の20%が休業特別支給金として支給されます。
(3)傷病補償年金(傷病年金):1年半経過しても傷病が治らない場合の補償
怪我や病気が1年6か月経っても治癒せず、一定の障害(1級~3級)がある場合、治療費の支払は継続したまま、休業給付に代えて傷病補償年金・傷病年金の支給があります。
(4)障害補償給付(障害給付):後遺障害が残った場合の補償
怪我や病気が治ゆ(症状固定)した後、後遺障害が残った場合には、障害等級第1級から第7級に該当する後遺障害の場合には障害補償年金(障害年金)が、障害等級第8級から第14級に該当する後遺障害の場合には障害補償一時金(障害一時金)が、それぞれ支給されます。
(5)遺族補償給付(遺族給付):死亡した場合の補償
労働者が死亡した場合には、その収入によって生計を維持していた家族に対して遺族補償年金(遺族年金)が、給付基礎日額の153 日~245 日分程度支給されます。ただし、妻以外の遺族はある程度高齢または年少であるか、一定の障害の状態にあることが受給要件となっているので注意が必要です。
遺族補償年金(遺族年金)の受給資格を持つ方がいない場合や、年金を受けている人が全て死亡などにより受給資格を失った場合には、遺族補償一時金(遺族一時金)として、給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
また、これらに加えて、遺族特別支給金として一律300万円が支給されます。
(6)葬祭料(葬祭給付):死亡した場合の補償
労働者が死亡した場合には、葬祭料(葬祭給付)も支給されます。支給額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額か、給付基礎日額の60日分の多い方の金額です。
(7)介護補償給付(介護給付):介護が必要になった場合の補償
介護補償給付(介護給付)は、傷病補償年金(傷病年金)、障害補償年金(障害年金)を受給する資格のある労働者が一定の障害の状態にあり、介護を受けているときに支給されます。
○労災保険と民事損害賠償の関係
労災保険の給付金とは別に、使用者に対して民事上の損害賠償責任を追及することができるケースがあります。それは、使用者が「安全配慮義務(健康配慮義務)」に違反している場合です。
まず問題となるのは、慰謝料です。労災保険には、慰謝料に相当する給付はありません。したがって、慰謝料については労災保険とは別途請求することができます。
また、死亡または障害により生じた逸失利益(その事故がなかったら得られたであろう利益)も、労災保険では全て補填されないことが多いですし、控除できるのはあくまで確定している金額のみですので、将来給付される年金は控除できません。
さらに、休業中の賃金についても、労災の休業補償では60%分しか支給されていません。
このように、労災保険は、慰謝料や逸失利益に対する賠償には十分に対応しておらず、労災保険で補填しきれない部分は、使用者に対して別途損害賠償請求をすることができることになります。
○どのような場合に使用者に損害賠償請求ができるか
(1)安全配慮義務違反
では、どのような場合に、使用者に対して損害賠償請求をすることができるのでしょうか?
労働契約において、使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければなりません。これを安全配慮義務といい、労働契約法5条に明記されています。
このように、使用者は、労働災害の発生を未然に防ぐために、あらゆることを想定して配慮することが求められており、使用者が配慮すべきことをしていなければ、この安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求責任を追及することができます。
この安全配慮義務という考え方は、かつては、主に製造業などの業種における薬品や重機の取扱いによる直接的な事故・身体的危害に対して適用されてきましたが、次第にメンタルヘルスや過労などの精神衛生面においても広く適用されるようになってきました。
今では、設備・作業環境といった物理的環境から、労働時間などの時間環境、さらには精神的な「気持ち」の部分まで、職場環境のあらゆる場面に安全配慮義務が発生しうる状況にあるといえます。
(2)結果責任ではない
損害賠償責任は、使用者に安全配慮義務違反がある場合にのみ請求できるものであり、結果責任ではありません。何らかの労働災害が生じ、労災認定が下りたとしても、イコール使用者が責任を負うというわけではなく、使用者が適切な災害防止策を講じていたと認められた場合には、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任は否定されます。
実務上は、この災害防止策について厳しく判断されるのが通例です。もっとも、「被災者が事故に遭ったのは、会社の安全配慮がこういう点で足りなかったからだ」という理屈付けを、労働者の側できちんと立証できないと、使用者の責任が否定されてしまうことがあります。
また、使用者の安全配慮義務違反が認められた場合でも、使用者がそれなりの対応を取っていて、労働者側に一定の落ち度があるといえるようなケースでは、過失相殺によって、賠償額が大きく減額される可能性があります。
したがって、使用者に損害賠償請求をするに当たっては、十分な立証資料を収集し、適切な主張を組み立てることがとても重要です。
(3)労災認定は必須ではない
労災認定が下りていなければ、使用者が責任を負うことはないというわけではありません。労災が認められていない場合でも、裁判所が安全配慮義務違反と損害との間の因果関係を認めて、損害賠償を命じることはあり得ます。
実務上も、労災の認定基準は満たしていないため、労災は通らない可能性が高い一方で、企業の責任は問われるべき事案では、労災認定の可否を裁判で争うという方法のほか、労災の認定を経ずに損害賠償請求の裁判を起こす、という方法も考えられます。
○誰が・誰に請求できるのか?
使用者の安全配慮義務は、パートやアルバイトといった非正規の労働者に対しても及びます。
また、派遣社員の場合、雇用契約は派遣会社との間にありますが、実際に作業の指導をするのは派遣先のため、派遣先が安全配慮義務を負うことになります。出向中の労働者の場合は、出向元・出向先の両社が、安全配慮義務を負うのが通例です。直接の雇用契約がない下請労働者に対しても、元請けの現場責任者が作業の指導などを行っていた場合には、安全配慮義務が認められることがあります。
上記のようなケースでは、安全配慮義務を負っている派遣先・出向先・元請会社に対して、損害賠償請求をすることを検討すべきです。
○いくら請求できるのか?
(1)高額賠償が認められた例
安全配慮義務違反による賠償事例では、もちろん事案によりますが、賠償額が非常に高額になることも多いです。
例えば、電通に勤めていた男性社員が1981年に過労自殺したという事件がありましたが、この件で、電通は、約1億6800万円の損害金を支払うことで遺族と和解しました。
また、解体工事の請負業者のアルバイト作業員が、工事現場の2階から転落し、脊髄損傷等の傷害を負って寝たきりの状態となり、労災で後遺障害等級1級が認定されたという事案では、労災から障害補償給付として約2000万円が支給されており、また1割の過失相殺が認められましたが、それでも、慰謝料や逸失利益、介護費用などの損害として、さらに約8000万円の賠償命令が出されました。
(2)賠償の内訳
労災保険からは、治療費を除く積極損害、例えば入院雑費、付添看護料、通院交通費・宿泊費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、弁護士費用といった積極損害については支給されませんので、損害賠償の対象になります。
また、休業損害は、労災からは60%分のみ支給されますので、残りの40%分は損害賠償の対象になります。
逸失利益についても、等級が軽い事案では一時金、重い事案では年金が労災から支給されますが、一時金は十分な金額ではなく、年金も将来給付分は賠償額から控除されませんので、不足する逸失利益については損害賠償の対象となります。
さらに、慰謝料については労災保険からは支給されませんので、損害賠償の対象となります。
○労災事故発生からの流れ
最後に、労災が起きてからの流れについて、事故により負傷したケースを例に、時系列に沿ってお話しします。
(1)事故発生
労災が発生した場合、まずは、被災者の救護が最優先です。重大な事故であれば、救急車の出動要請や警察への通報、負傷者の家族への連絡、他の従業員らの避難などが行われます。また、病院が、治療にかかった費用を労基署に請求しますので、労基署への連絡も通常は使用者から行います。病院は、労災保険指定医療機関でないと、一旦立て替えることにはなりますが、後日戻ってきますので、何よりも早く治療することが最優先です。
(2)治療
労災の治療のためには、病院に、療養補償給付の申請書を提出する必要があります。労災保険指定医療機関以外の病院の場合には、一旦治療費を立て替えて支払った上で、後日、その費用を労基署に請求することになります。
また、休業した場合には、休業補償給付の請求書を、その都度提出します。
(3)症状固定
その後、治療を続け、症状固定に至った段階で、後遺症が残っている場合には、医師から診断書を取り付けて、障害補償給付の申請を行います。
なお、1年半経過しても症状固定に至らず、一定の障害がある場合には、まずは傷病補償金を請求し、症状固定後に障害補償給付の申請を行うことになります。
(4)労災認定、異議申立て、取消訴訟
後遺障害の認定が下りると保険金が支給されます。認定に対しては、異議の申立てを行うことができ、それでも認められなければ、取消訴訟で認定の可否を争うこともできます。
(5)民事損害賠償の請求
以上により、労災の結果が確定した段階で、労災の給付では不足する部分について、使用者に対する民事損害賠償請求の交渉が開始するのが通常です。
ただし、先ほど述べたように、労災の認定は下りない可能性がある場合など、必ずしも労災の認定を経ずに、損害賠償請求をするようなケースもあります。
○労災に遭ったら、すぐに弁護士にご相談を
以上のように、労災保険の手続や、使用者に対する損害賠償請求は、一般の方にとっては難しい面も多いです。適切なタイミングで、適切な補償を受けるために、早い段階から、労災事故に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士法人江原総合法律事務所では、労災事故に遭われた労働者や遺族の方から多数のご相談を受け、労働者や遺族の方の立場に立って、労災申請のサポートや使用者に対する損害賠償請求の案件を取り扱ってきた実績があります。
初回相談料は30分まで無料ですので、是非お早めにご連絡ください。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
24時間受付